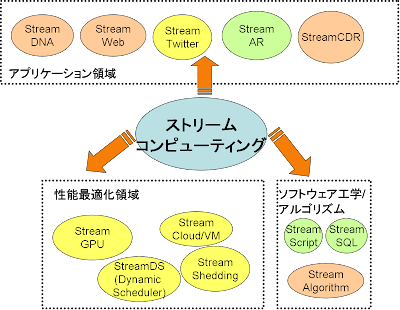良い論文を書く(=国際会議に通す)上で必要なことを書きます。
(1) 実装を始める前に、徹底的に既存研究を調査し、それとの差異を明確にする。差異が明確にできたら、深い実装を始める前にスライドに一つの筋書きが書けるはずです。研究によっては、少し実装を始めなければわからないこともあるでしょう。この際にはできるだけ、クイックにプロトタイプ実装し、iterative に(1) を繰り返していきましょう。
(2) 実装中には、新たな技術的発見、既存研究との差異をより明確化するような要素を見つけてください。その研究の価値が集りますし、新規性を主張しやすくなります。
(3) 実装が終了した後は、徹底的な定性的・定量的評価をしてください。(a) 評価対象アプリケーション・シナリオの豊富さ(マイクロベンチマーク、実アプリケーションを含めて3つが定石)、(b) 提案手法の優位性を示すデータ、(c) (b)に関するプロファイリング(なぜ良くなったか、なぜ悪いかを定量的に示す)(d) 類似技術との比較、の4点セットが必須です。特にほっとして(3)が poor になりがちですが、非常に大切です。
論文は最終的に国際会議(査読付き)に通してこそ、その研究が終了したと思ってください。(1) の段階で研究の方向性を変えていくことは悪いことではありません。むしろ研究の方向性が間違ったまま突っ走ることこそ良くありません。但し、(2) まで進んだ際には必ずその研究をしっかりと完遂していきましょう。
関連エントリ
gnuplotでeps
13 年前